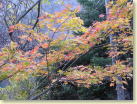| 日時 2004年11月13日 天気 登山コース 行者還トンネル西口 ⇒ 奥駈道出合 ⇒ 弁天の森 ⇒ 聖宝ノ宿跡 ⇒ 弥山小屋(休憩・山頂探す迷走40分) 8時45分 9時35分 10時 10時30分 11時20分 八経ヶ岳山頂(昼食・展望1時間) ⇒ 弥山小屋 ⇒ 奥駈道出合 ⇒ 行者還トンネル西口 12時25分 15時20分 (歩数 26143歩) 如何しても八経に登りたい! あと1ケ月で林道のゲートが閉められ、来年4月下旬まで登れない!(他からも登れるが、中級者コースなので私には無理) 天気も良さそうなので思い切って行く事にしました。 朝5時起床、前日に用意していなかった為、家を出たのが6時過ぎです。 こんな時間に出て登れるかな〜と思いながらの出発!! 途中、何時ものようにコンビニでお昼のおにぎりを買って、行者還トンネル西口に着いたのが、8時半頃でした。 天川村からR309は、大川口付近の落石で通行止なので、R169からR309の林道に入ります。 クネクネ道ですが舗装された1.5車線で対向も出来ます。 道沿いの樹木は見頃を少し過ぎた紅葉、アマチヤカメラマンが望遠レンズの付いた一眼レフを持って側道を歩いています。 長い行者還トンネルを抜ければ右手、川との間に駐車場があり、先客が7台駐車しています。一段下にもスペースがあってマイクロバスも 停まっています。ツアーで来た団体のようで運転手が外で暇そうにタバコを吸っています。 準備をしていよいよ出発! 林道を暫く歩くと丸太で造った橋があり川を渡り、ここからシャクナゲの木が茂る急な登りが続き、奥駈道出合に出ます。 主稜線を走る奥駈道は国内で最も古い歴史を持つ山岳古道の一つです。 上方が明るく開けていて周囲の展望も良く、起伏を上下して歩き、石休場宿跡を過ぎると弥山の尾根が見えて来ます。 三角点のある弁天の森では中腹がガスにかかった弥山・八経の両山頂が、 ブナの原生林を進むと聖宝ノ宿跡で、ここから弥山小屋まで「聖宝八丁」への急な登りです。 残業が続き、3時間の睡眠で山登り、この急坂はこたえます。後ろを登ってくる登山者に道を譲る。若い人なら良いが、年配の夫婦に抜かれる とカッコ悪い気がして、写真を撮るフリをする。
山中にそぐわない機械音が聞こえてきます。弥山小屋の発電機の音… 登り始めから約2時間半で弥山小屋に到着! はぁ〜しんど! 暫しの休憩 鳥居をくぐって周囲が白骨林の中を進めば、天河弁財天奥宮があります。 ここからトウヒやシラベの原生林でおおわれた八経ヶ岳が目の前に、八経ヶ岳の中腹や明星ヶ岳の山頂は、霧氷で樹木が白いです。 弥山の頂上は、地図でこの付近の筈、八経や稲村、大普賢のように尖っていないのでわかりません! 奥宮で休憩している人に聞いてみると、向こうの(奥宮の北)倒木の中とのこと。確かに此処より高いような〜 感じが?、 弥山小屋の裏手に僅かに足跡があるブッシュ地帯をだいぶ進みましたが、何処が高いのかわかりません! 木の枝で顔を擦り、シャツが倒木に引っ掛かり破けました。 コロンビアの速乾・撥水加工のシャツが…、高かったのに…、滅多に買わない赤系… ああァ〜。。。 結局は、何処が山頂かわかりませんでした。 多分、鉄山の方へ行く登山道に入ってしまったのだと思います。 本当に、あの人は知っていたのだろうか? 弥山小屋に戻ったのがお昼、お弁当を広げているグループが何組かいます。 腹減った!!
弥山小屋から樹林を鞍部まで下がり、オオヤマレンゲの自生地をシカの食害から守るため網が張りめぐらされています。 扉を開けて入り急坂を登れば八経ヶ岳の山頂です。 誰もいない! 弥山にかかっていたガスも切れ、稲村・山上・大普賢・行者還、そして弥山に続く奥駈道、大台ヶ原の山々が見渡せます。 後の人が登ってくるまでの間、30分ぐらい、この絶景を一人楽しみました。(=^^=) 今、近畿で一番高い地に立っているのだと思うと嬉しくなり、まして今日は、好天に恵まれ大峰の山々が展望抜群です。 あァ〜来て良かったなと思う。
山頂で昼食にする。 食後のコーヒーは、本当に美味しかった。 風も無く日差しが強くて、寒くは感じなかったが、木々には霧氷があり、気温4度でした。 写真をいっぱい撮って下山する事にしました。 今年の7月から稲村、大普賢、弥山・八経と登りましたが、近くの山なのに山容や植生が違います。 また、同じ山でも季節や天候で全く違う事を感じました。 新緑の頃やオオヤマレンゲの咲く頃、この山に登ってみたいです。 『八経ヶ岳山頂からのパノラマと弥山国見八方覗からの展望』
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||